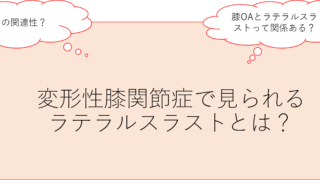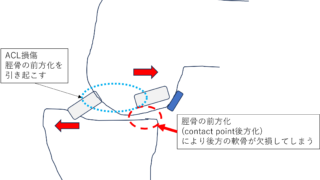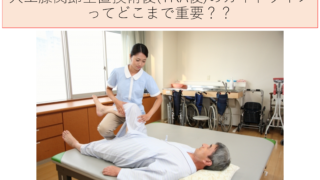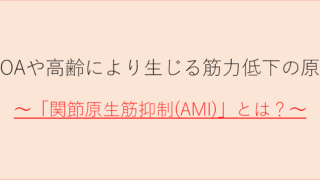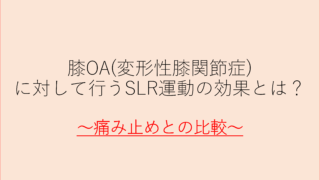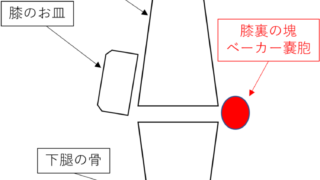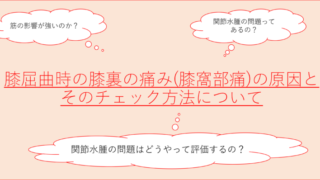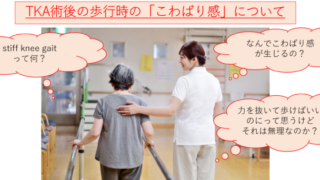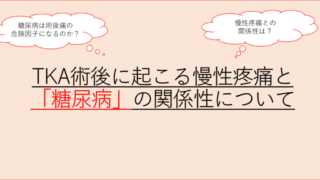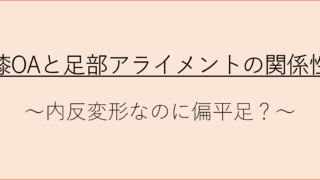 変形性膝関節症(膝OA)
変形性膝関節症(膝OA) 変形性膝関節症(膝OA)と足部アライメントの関係性~内反変形なのに偏平足?~
今回は、変形性膝関節症(膝OA)患者の足部アライメントについて考えていきたいと思います。膝関節が内反なので、骨盤は後傾、それに伴って股関節は外旋するから足部も回外位になるか…といった固定概念をもったことはないでしょうか?実際の臨床現場では、足部の内側縦アーチは潰れ、偏平足や外反母趾を呈したケースが非常に多いわけです。今回はそういった疑問点(私だけかもしれませんが…)についてまとめていきたいと思います。